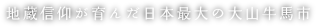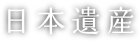STORY 牛馬の聖地
江戸時代には日本三大、明治時代には日本最大の牛馬市となった大山牛馬市のきっかけは些細なことだったと伝わっています。
そもそも大山にはいつから牛馬がやってきたのでしょうか。平安時代に書かれた『本朝法華験記』には明蓮(みょうれん)という僧の説話が収録されています。明蓮の前世は牛で、かつて大山の宿坊に連れてこられていたという過去が明かされます。この頃には既に牛馬が集まる下地ができていたと考えられます。『本朝法華験記』には「粮米を牛に負はせて」とあり、牛馬には長旅の食料を運ばせていたことが分かります。大山に集まった牛馬は、はじめは「牛馬信仰」のためではなく、あくまで荷負のために連れてこられていたのです。
明蓮の前世と同じように、牛馬は持ち主が参拝している間、宿坊や境内前の広場に繋がれていました。そして、ある時、繋がれていた牛を見た人が「なんとええ牛だいや。」と他の人の牛に見惚れたのでしょう。中にはその牛よりも自分の連れているほうが立派な牛だと思った人もいました。こうしてそれぞれの自慢の牛馬を比べる牛比べ・馬比べがはじまりました。
その牛比べ・馬比べに参加している牛馬を手に入れたいと思う人も数多くいました。彼らは競うようにその牛馬の価値を決めていきます。物々交換から次第に金銭の授受が生まれ、やがて牛馬が売買されるようになりました。牛馬市の誕生です。
江戸時代中期にはこの牛馬市の経営に大山寺が乗り出しました。市が開かれたのはそれまで牛比べ・馬比べが行われていた境内前の広場です。大山寺が市を開くようになると広場には多くの博労(馬喰とも。牛馬を売買する商人のこと。)が集まるようになりました。境内前の広場は博労座と呼ばれるようになり、今もそう呼ばれています。
しかし、鉄道が発達すると、それまで1人が数頭ずつ連れてきていたのに比べ、何十頭と一度に運べるようになります。輸送効率の良さから牛馬市は鉄道沿線で行われるようになっていきます。そうして大山牛馬市は鉄道沿線で行われるようになっていきます。そうして大山牛馬市は昭和12年に幕を閉じます。博労座で牛馬を見ることもなくなりました。
そんなかつての牛馬の聖地博労座を舞台に、大山をもっと盛り上げようという試みがなされています。「牛馬の聖地 大山ドリームカーフェスタ」はその1つです。猛牛のエンブレムで有名なランボルギーニ、跳ね馬のエンブレムで有名なフェラーリなどの集まる、「現代版牛馬の聖地」として復活させようというイベントです。昨年度開催した際には1日で1万人、今年度は雨の中4,000人のご来場がありました。